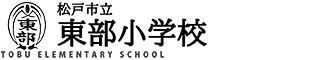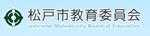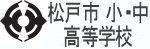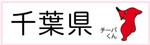11月の給食
| 4日 |  |
ロールパン はなやさいのシチュー カリカリじゃこのサラダ パインアップル ぎゅうにゅう |
|
今日の給食はロールパン、花野菜のシチュー、カリカリじゃこのサラダでした。サラダの歴史は非常に古く、その原型は古代ギリシャ時代にまでさかのぼると言われています。野草に塩を振って食べたのがルーツです。語源はラテン語の「sal(塩)」に由来するとされ、「herba salata(塩味の草)」が英語の「salad」の原型になったと言われています。古代ローマ時代には、オリーブオイルや酢、塩漬けの魚などで味付けをしたものが登場し、贅沢なサラダもあったようです。日本で「サラダ」という食文化が定着し始めたのは、明治時代以降、欧米の食習慣が入ってきてからです。とんかつの付け合わせの千切りキャベツが普及のきっかけの一つだったとも言われています。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 5日 |  |
えだまめごはん こうやどうふのあげに みそしる きっかみかん ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、枝豆ご飯、高野豆腐の揚げ煮、みそ汁でした。枝豆(大豆)は古代からの栽培されており、未熟な大豆のことをいいます。大豆そのものは中国で約4000年前から栽培されていたと考えられています。日本には弥生時代初期に中国から伝来し、アワやヒエとともに主食の一つとして畑で栽培されていました。若いさやを食べる、現在の「枝豆」という食べ方が普及したのは、江戸時代に入ってからです。江戸時代には、枝についたまま茹でられたものが売られ、食べ歩きをしていたことから「枝豆」の名がついたと言われています。当時の枝豆は、主に酒の肴(おつまみ)として庶民に親しまれていました。枝豆ご飯については、旬の豆類を炊き込みご飯や混ぜご飯として楽しむ日本の食文化の中で自然に生まれたと考えられます。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 6日 |  |
プルコギどん わかめととうふのスープ しらたまのくろみつきなこ ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、プルコギ丼、わかめと豆腐のスープ、白玉の黒蜜きな粉でした。プルコギ(불고기)は、韓国を代表する肉料理であり、「プル(불)=火」と「コギ(고기)=肉」を意味し、直訳すると「火で炙って食べる肉」です。その歴史は古く、時代とともに調理法が変化し、現在の甘辛い味付けのスタイルが確立されました。私たちが知る「甘辛いタレに漬け込んだ薄切り肉を、汁気とともに焼く・煮る」スタイルは、比較的近年に確立・普及したものだそうです。朝鮮時代に、宮廷料理のノビアニというもの近い料理があったのですが、調理に時間がかかりすぎたため、戦後、庶民の食堂において、調理時間を短縮し、硬い肉を柔らかく食べさせるために、肉を薄く切る調理法が流行し始め、客が自分で肉を焼いて食べる現在のプルコギスタイルになりました。この時期に、現在の特徴である甘辛い味付けが広く普及したとされています。今日の東部小のプルコギもおいしかったです。 | ||
| 7日 |  |
ちゅうかどん ポップビーンズ フルーツポンチ ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、中華丼、ポップビーンズ、フルーツポンチでした。フルーツポンチの語源は海外にありますが、現在日本で一般的に親しまれている「シロップやサイダーにたくさんのフルーツを漬け込んだデザート」の形は、日本独自で発展したものと言われています。語源「ポンチ(Punch)」の起源は、英語の「パンチ(Punch)」が訛ったものです。パンチの語源は、ヒンディー語で「5」を意味する「パーンチ(Panch)」に由来します。これは、17世紀にインドに駐在していたイギリス人(東インド会社)が、5種類の材料(水、砂糖、酒、ライム果汁、スパイスなど)を混ぜて作ったカクテルの名前として定着したものです。このパンチはイギリスを通じて世界に広がり、その後、果物を加えたものが「フルーツ・パンチ(Fruit Punch)」と呼ばれるようになりました。日本には、オランダ語の「ポンチ(Pons)」などの影響もあり、ポンチという呼称が定着しました。日本で現在のフルーツポンチの原型が誕生したのは、明治時代だとされています。東京の老舗果物専門店「銀座千疋屋」の二代目(斎藤義政氏)が発案したという説が有力です。彼は、カクテルである「フルーツ・パンチ」から着想を得て、果物と洋酒の割合を逆転させ、主役を果物にしたデザートとして開発し、「フルーツポンチ」と名付けました。現在では、日本独自の進化を遂げ、季節を問わず愛される和製洋風スイーツの代表格となりました。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 10日 |  |
ごはん いわしのねぎみそまき のりあえ のっぺいじる プチぎゅうにゅうプリン ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、ご飯、鰯のネギ塩巻き、海苔和え、のっぺい汁でした。のっぺい汁(のっぺ汁、ぬっぺい汁などとも)は、日本全国に分布する郷土料理であり、特に精進料理を原型とする歴史の古い煮物です。地域によって具材や呼び名が大きく異なるのが特徴です。「のっぺい汁」という名前の明確な起源は一つに定まっていませんが、有力な説がいくつかあります。最も有力な説は、「のっぺ」や「のっぺい」が、汁にとろみをつけること、または、とろりとした状態を意味する言葉に由来するというものです。里芋のぬめりや片栗粉でつける、独特のとろみ(ぬめり)が名前の由来と考えられています。のっぺい汁の原型は、仏事や法事などで振る舞われる精進料理として古くから存在していました。昔は、葬式やお盆、彼岸の時期に、地区の女性たちが肉類を使わない野菜と豆腐、油揚げなどを使った精進の汁物として作っていました。薄味でやわらかく煮込まれ、昆布や椎茸の精進だしが使われるのが特徴です。片栗粉や葛粉でとろみをつけるのは、具材を汁から引き揚げやすくするだけでなく、料理を冷めにくくするためでもあります。これは、一度に大勢に振る舞う際の知恵でもありました。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 11日 |  |
スパゲッティ・ミートソース えだまめサラダ バナナチョコチップケーキ ぎゅうにゅう |
| 今日は、口のまわりをオレンジ色にしてしまう子どもたちに大人気のミートソースです。白い洋服を着てきた子は、シミを作って帰っていませんか?味が濃厚で、パスタに絡みやすく、フォークが止まらないおいしさです。そして、今日は何と!「バナナチョコチップケーキ」です。チョコチップをふんだんに使ったケーキはどこを食べてもチョコ!が楽しめます。ふっくら焼き上げたケーキは幸せを運んできました。今日は幸せいっぱいの給食でした。ごちそうさまでした。 | ||
| 12日 |  |
カレーライス コーンサラダ オレンジ ぎゅうにゅう |
| 今日の給食はカレーライス、コーンサラダでした。カレーライスは、今や日本の国民食として深く浸透していますが、その背景にはイギリス、インド、そして日本独自の面白い歴史とエピソードがあります。カレーはインド発祥ですが、日本には直接インドからではなく、イギリスを経由して伝わりました。18世紀に東インド会社の社員がスパイスとお米をインドからイギリスに持ち帰り、王室や富裕層の間で人気となり、簡単にカレー料理を作るための「カレー粉」が開発されました。このカレー粉が、明治時代初期(1870年頃)の文明開化の波に乗って日本に伝わりました。純インド式カレーは、1927年(昭和2年)に、東京の「新宿中村屋」が喫茶部を開業し、純インド式カリ・ライスを、当時の大衆食堂の10倍の値段(80銭)で提供し、高値にもかかわらず人気を博しました。これが日本で最初の本格的なインドカレーとされています。インドのカレーは、基本的にサラサラしていますが、日本のカレーの特徴である小麦粉を使った「とろみ」は、実はインドではなくイギリスで加えられ始めたものと言われています。今日の給食もおいしかったです。 | ||
|
13日 |
 |
とりごぼうめし ししゃものいそべあげ ごまあえ かきたまじる きっかみかん ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、鶏ごぼう飯、ししゃもの磯部揚げ、ゴマ和え、かき玉汁でした。私たちが日常的に食べている「ししゃも」には、実は多くの人が知らない興味深い事実が詰まっています。最大のポイントは、「本ししゃも」と「カラフトシシャモ」は全くの別物である、ということです。スーパーや小売店などで一般的に「ししゃも」として売られているものの約9割以上は、実は「カラフトシシャモ(カペリン)」という代用魚です。本ししゃも(シシャモ)は日本固有種で、北海道の太平洋沿岸のみ(鵡川、十勝川など)に生息している希少な高級魚のことをいいます。一方、カラフトシシャモ(カペリン)は、北大西洋(ノルウェー、アイスランドなど)や北太平洋に広く分布しており、大量に漁獲され、冷凍で輸入される安価な魚として流通しています。「ししゃも」という名前は、その希少性と文化的背景に由来します。「ししゃも」の語源は、北海道の先住民族であるアイヌ語の「スス・ハム(Susu-ham)」に由来します。「スス」は柳(やなぎ)、「ハム」は葉(は)を意味し、「柳の葉から化けた魚」という意味があります。アイヌの人々にとって、シシャモは冬を越すための貴重な食料として崇められていました。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 14日 |  |
ごはん さばのしおやき ひじきとだいずのにもの とんじる りんご ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、ご飯、鯖の塩焼き、ひじきと大豆の煮物、豚汁でした。豚汁(ぶたじる、または、とんじる)は、日本の家庭料理として非常に親しまれていますが、そのルーツは江戸時代の薩摩藩(現在の鹿児島県)にあり、軍隊を通じて全国に広まったという歴史的背景を持っています。江戸時代、日本では仏教の影響で獣肉食は一般的に禁忌とされていました。しかし、薩摩藩では、豚やイノシシ、鹿などの獣肉を食べる独自の食文化が維持されており、特に豚肉が重宝されていました。薩摩汁は、この鶏肉や豚肉、兎肉などの獣肉と、芋やごぼうなどの根菜を煮込み、味噌で調味した味噌汁でした。明治時代に入り、肉食禁止令が解かれ、特に栄養価の高い豚肉や牛肉が利用されるようになりました。旧日本陸軍は、栄養価が高く、調理が容易な豚肉入りの味噌汁を炊事マニュアルに取り入れました。1909年(明治42年)頃に発行された陸軍の炊事マニュアル「軍隊料理法」にも「薩摩汁」の項目があり、「豚(又は鶏、兎、羊肉)を、芋やごぼう等と煮て味噌汁にする」と記載され、豚汁は薩摩汁の一種として位置づけられました。豚汁は、日本の厳しい食の歴史、地方独自の文化、そして近代日本の軍事・社会的な流れが複合的に作用して、現在の国民的な地位を確立した料理と言えます。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 18日 |  |
ごもくうどん わかさぎのフリッター だいこんときゅうりのピリッとあえ みそやきおにぎり ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、五目うどん、ワカサギのフリッター、大根とキュウリのピリッと和え、味噌焼きおにぎりでした。五目うどんの「五目(ごもく)」は、必ずしも5種類の具が入っているという意味ではありません。「いろいろな~」 や 「多種類の~」 という意味合いで使われています。同様に、中華料理の八宝菜(はっぽうさい) の「八」も、「たくさんの」という意味で使われているそうです。東京や西日本の一部地域では五目うどんのことを「おかめうどん」 と呼ばれることもあるそうです。「おかめ八目(おかめはちもく)」という言葉に由来するとされています。五目うどんは、栄養バランスを考えてお肉や野菜など様々な食材が使われる、賑やかでおいしい一杯なんですね。今日は、寒い一日だったので、うどんの温かさが一段と際立つ給食でした。とてもおいしかったです。 | ||
| 19日 |  |
こぎつねごはん さけのもみじやき こぶちゃあえ みそしる ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、子ぎつねご飯、鮭の紅葉焼き、昆布茶和え、みそ汁でした。みそ汁の歴史は、平安時代の頃、味噌は今のようにお湯に溶かして飲むものではなく、主に野菜につけて食べる(なめ味噌のような)ものでした。室町時代に入り、味噌をすりつぶして汁に溶かす、現在のみそ汁の原型となる食べ方が広まりました。戦国時代には、味噌は、兵糧(軍隊の食糧) や先陣食として欠かせないものとなりました。栄養価が高く、持ち運びやすい味噌は、戦国武将たちに重宝されました。江戸時代に入り、庶民の食卓に欠かせないものとなり、「一汁一菜」という食文化の基本を支える汁物として定着しました。ちなみに、「みそ汁は沸騰させるな」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは、味噌に含まれる香気成分の中には加熱によって揮発しやすいものがあり、沸騰させることで風味が飛んでしまうためだそうです。ただし、赤味噌(八丁味噌など)は約2年と熟成期間が長く、タンパク質がしっかり分解された濃厚な旨味が美味しいため、味噌煮込みうどんのように煮込んでも旨味が残りやすいという特徴があります。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 20日 |  |
ミルクパン しゃきしゃきハンバーグ あおなともやしソテー コーンクリームスープ きっかみかん ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、ミルクパン、シャキシャキハンバーグ、青菜ともやしのソテー、コーンクリームスープでした。コーンクリームスープの主役であるトウモロコシが世界に広がる背景には、歴史的な出来事があります。トウモロコシは、コロンブスがヨーロッパ大陸に持ち帰ったことをきっかけに、瞬く間に世界中に広まりました。日本への伝来は16世紀後半にポルトガル人によって日本に伝えられました。日本国内でのトウモロコシ(スイートコーンなど)の普及に大きな影響を与えたのは、アメリカから新種を輸入し栽培を始めた北海道での取り組みでした。明治時代の北海道開拓期に、北海道では気候が冷涼で土壌条件も厳しく、当時の主食であった米や麦の栽培が困難でした。そこで、アメリカから輸入したトウモロコシを栽培したわけです。比較的冷涼な気候でも育ちやすく、乾燥にも強いという特性があり、北海道の気候条件にあったということですね。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 21日 |  |
ゆかりごはん なまあげのかりんあげ からしあえ けんちんじる ぎゅうにゅう |
|
今日の給食は、ゆかりご飯、生揚げのかりん揚げ、からし和え、けんちん汁でした。「ゆかり」は、日本の食卓で広く愛されるロングセラー商品であり、その名前には美しい意味が込められています。1970年(昭和45年)に三島食品株式会社から発売されました。発売から半世紀以上にわたり、赤しそを使ったふりかけの定番として親しまれています。開発のきっかけは、「ゆかり」の発売前、広島よりも名古屋(中京地区)の方が、赤しそを食べる文化が根付いており、販売店で赤しそがたくさん売れているという情報が、商品開発のきっかけの一つになったそうです。ネーミングの由来は、①古代の日本では、「紫」という色を意味する言葉として「ゆかり」が使われることがありました。これは、古今和歌集などに詠まれた歌で、「紫草(むらさき)」が生える土地を指す言葉が「ゆかり」に転じたことに由来するといわれています。②「ゆかり」は、「縁(えん)」という意味もあります。三島食品は、「ご縁」を大切にしたいという願いから、この名前を採用したそうです。ゆかりは商品名だったんですね。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 25日 |  |
コッペパン いちごジャム あじのハーブやき ジャーマンポテト はくさいとぶたにくのスープ ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、コッペパン、いちごジャム、鯵のハーブ焼き、ジャーマンポテト、白菜と豚肉のスープでした。ジャーマンポテトは日本生まれの創作料理であることを皆さんは知っていましたか。日本で一般的に知られる「ジャーマンポテト」(茹でたジャガイモをベーコンや玉ねぎと一緒に炒め、塩胡椒などで味付けする料理)は、戦後の日本で生まれた創作料理である可能性が高いです。「ジャーマン(German)」は「ドイツ風」を意味しますが、これは当時の日本において、西洋風や異国情緒を演出するため、料理名に外国語を用いる傾向があったことから付けられたと考えられています。本場ドイツのジャガイモ料理にヒントを得て、日本でアレンジされて広まりました。日本人がイメージするジャーマンポテトに最も近いドイツの家庭料理は、「Bratkartoffeln(ブラートカルトッフェルン)」といいます。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 26日 |  |
カレーマーボーどん はるさめスープ きっかみかん ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、カレーマーボー丼、はるさめスープでした。東京都大田区の蒲田にある町中華の老舗「寳華園(ほうかえん)」(創業1965年・昭和40年)では、二代目の店主が「自分の大好きなカレーライスと麻婆豆腐を合体させたらさぞおいしくなるだろう」という思いから、試行錯誤を重ねて約10年かけて「マーボー豆腐風カレー」を開発したというエピソードがあります。牛丼チェーンの松屋では、2008年に「マーボカレー」が発売され、当時人気メニューとなりました。これにより、より多くの人に「カレーと麻婆豆腐を組み合わせた料理」が知られるようになりました。カレーマーボーは、麻婆豆腐が日本で普及した後、さまざまな場所で中華料理とカレーライスという日本の食文化に深く根付いた2つのメニューを融合させるアイデアとして生まれたものと言えるのではないでしょうか。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 27日 |  |
ごまみそラーメン きびなごポテトフライ うめかあえ こめこのマドレーヌ ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、ゴマ味噌ラーメン、きびなごポテトフライ、梅香和え、米粉のマドレーヌでした。マドレーヌは、フランスを代表する焼き菓子の一つで、その歴史にはいくつかの興味深い説があります。共通しているのは、フランス北東部のロレーヌ地方が発祥の地とされ、「マドレーヌ」という名の女性にちなんで名付けられたという点です。マドレーヌの起源として最も広く知られているのは、18世紀半ば(1755年頃)のフランス、ロレーヌ地方コメルシーの館でのエピソードです。当時ロレーヌ公であった元ポーランド王スタニスラス・レクチンスキー公が館で晩餐会を開いていた際、料理人とパティシエが口論の末、仕事を放り出して館を出て行ってしまいました。デザートがなくなり困窮した厨房を救うため、館にいた若い召使いの女性「マドレーヌ」が、祖母から教わっていた素朴な焼き菓子(あり合わせの材料とホタテ貝の殻を型にして作ったとされる)を急遽作って提供しました。スタニスラス公はその焼き菓子の美味しさに大変感動し、危機を救ってくれた彼女の名前をとって、このお菓子を「マドレーヌ」と名付けた、と伝えられています。今日のマドレーヌは、米粉を使っていました。本場のマドレーヌと遜色のないおいしさでした。 | ||
| 28日 |  |
まいたけピラフ にくだんごのスープ キャラメルポテト ぎゅうにゅう |
| 今日の給食は、まいたけピラフ、肉団子のスープ、キャラメルポテトでした。ピラフのルーツはトルコ料理の「ピラウ(Pilav)」とされ、これがヨーロッパ、特にフランス語圏で「ピラフ(Pilaf)」として広まりました。バターの油で米を炒めてから、ブイヨン(出汁)と具材を加えて炊き上げる、洋風の炊き込みご飯のような料理です。ピラフ自体は、明治時代以降の西洋料理として日本に伝わり、広く知られるようになりました。「ピラフ」という言葉が日本の文献に登場する具体的な初期の例としては、1936年(昭和11年)の古川ロッパの日記に「カレースープに、松茸と舌平目のピラフ」という記述があります。このことから、少なくとも戦前には、高級な洋食メニューとしてピラフが認識され、提供されていたことがわかります。今日の東部のピラフは、まいたけがよいアクセントになっていて、とてもおいしかったです。 | ||