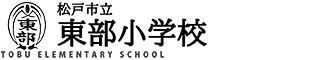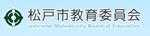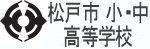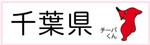9月の給食
| 2日(火) |  |
ナン キーマカレー えだまめサラダ パインアップル 牛乳 |
|
2学期最初の給食は、ナン、キーマカレー、えだまめサラダでした。ナンのルーツは古代ペルシャ(現在のイラン地域)にあり、約7,000~8,000年前に誕生した世界最古のパンの一つとされています。タンドールという窯の内側に生地を貼り付けて焼く製法が特徴で、ムガル朝時代にインドに伝わり、北インドの宮廷料理として広がりました。日本ではカレーに添えるイメージが強いですが、インドではチャパティといった他のパンが日常食であり、ナンは高級料理とされることもあります。今日の東部小のナンも高級だったのか、もちもちでとてもおいしかったです。 |
||
| 3日(水) |  |
プルコギどん わかめととうふのスープ ポップビーンズ 牛乳 |
|
今日の給食は、プルコギどん、わかめととうふのスープでした。韓国料理のひとつで、発祥は高句麗時代の朝鮮半島といわれています。 「プル」は火、「コギ」は肉を表します。 ただ、単純に火を通した肉をプルコギというのではなく、牛肉を甘辛いたれに漬けて下味を付けてから焼くのが特徴です。高麗時代(918-1392年)から存在していたとされる文献があります。 当時は「ネウビギ」(여우고기、現在のプルコギに近い調理法)と呼ばれていました。 しかし、現在のような甘辛い味付けは20世紀になってから広まったものです。今日もおいしくご飯が進みました。とてもおいしかったです。 |
||
| 4日(木) |  |
ごはん さばのしおやき ひじきとだいずのにもの みそしる なし 牛乳 |
| 今日の給食は、鯖の塩焼き、ひじきと大豆の煮もの、みそ汁でした。昔から「サバを読む」という言葉があります。数をごまかす際に用いられることわざです。市場で鯖を数える際に、早口で読み数をごまかしていたことからと言われているそうです。また、「サバの生き腐れ」ということわざは、新鮮に見えても腐っていることがあるということわざです。サバは鮮度の落ちが激しい魚です。サバにはアミノ酸の一種であるヒスチジンが多く含まれており、死後ヒスタミンに変化します。ヒスタミンは一定量を超えると中毒症状を引き起こす可能性があるためこのようなことわざができました。たくさんのことわざがあるように、昔から食べられていたことがわかりますね。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 5日(金) |  |
コーンちゃめし エビとうふのチリソースに・ポテトぞえ もずくいりたまごスープ 牛乳 |
|
今日の給食は、コーン茶飯、エビ豆腐のチリソース・ポテト添え、もずく入り卵スープでした。今日の給食は、エビチリではありませんが、エビチリの元になった料理は、中国四川料理の 「乾焼蝦仁(カンシャオシャーレン)」 というメニューだそうです。これはエビを辛味のあるソースで炒めたもので、唐辛子と豆板醤をたっぷり使うため非常に辛いのが特徴です。しかし、日本では辛さを抑えたマイルドな味付けが好まれるため、日本人向けにアレンジされたのが現在のエビチリだそうです。日本で生まれた料理だとは、あまりしられていませんね。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 8日(月) |  |
スパゲッティ・ミートソース コーンサラダ スイートビーンズポテト 牛乳 |
| 今日の給食は、スパゲッティ・ミートソース、コーンサラダ、スイートビーンズポテトでした。スパゲッティ・ミートソースのルーツはイタリアの「ボロネーゼ」ですが、日本で親しまれているミートソースはアメリカでアレンジされたものが起源とされています。これはイタリア系移民がアメリカで「ボロネーゼ」を元にミートソースを作り、それが第二次世界大戦後にアメリカの進駐軍を通じて日本に伝わり、ケチャップや砂糖を加えるなど、日本人の舌に合うようにさらにアレンジされたものだそうです。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 9日(火) |  |
ゆかりごはん なまあげのかりんあげ きくとやさいのおひたし とんじる 牛乳 |
| 今日の給食は、ゆかりご飯、生揚げのかりん揚げ、菊と野菜のお浸し、豚汁でした。9月9日(火)は、重陽の節句(ちょうようのせっく)と呼ばれ、別名「菊の節句」ともいいます。五節句の一つであり、陽数である「9」が重なる日として、平安時代の宮中では無病息災や長寿を願って菊の花を飾り、観菊の宴を開いたことが起源だそうです。菊酒を飲んだり、菊を飾ったお料理をいただいたり、菊湯に浸かるなどの風習があります。今日の給食はそれにちなんで、菊と野菜のお浸しが出ました。とても美味しかったです。 | ||
| 10日(水) |  |
ちゅうかどん フルーツポンチ だいずこざかな 牛乳 |
| 今日の給食は、中華丼、フルーツポンチ、大豆小魚でした。中華丼は、名前に「中華」という言葉を含みながら、以外にも日本発祥の料理であることを皆さんは知っていますか。中国ではほとんど食べられておらず、日本でも本格的な中華料理店では、メニューに載っていないことが多いそうです。広東料理では、「八宝菜」があります。これをご飯の上にのせたものが、中華丼です。諸説ありますが、昭和初期に、スタッフの賄いで出されたとか、お客さんが「八宝菜をご飯にのせてほしい」と言ったとか・・・。とにかく、昭和初期に東京で丼ブームが起こっており、そのときに生まれた料理であろうことはわかっています。今日の東部小の給食もおいしかったです。 | ||
| 11日(木) |  |
こくとうパン さけのハーブやき あおなともやしのソテー マカロニスープ オレンジ 牛乳 |
|
今日の給食は、黒糖パン、鮭のハーブ焼き、青菜ともやしのソテー、マカロニスープでした。鮭は白身魚であることを皆さんは知っていますか?実は、餌の甲殻類に含まれる色素「アスタキサンチン」のせいで身が赤くなっているそうです。また、産卵のために生まれた川に戻る「母川回帰」の習性を持つことも特徴のひとつです。日本では「サーモン」と呼ばれることがありますが、これはノルウェー人が日本の回転寿司に生食用のサーモンを広めるために「鮭」と区別して名付けたものです。今日の鮭のハーブ焼き、とてもおいしかったです。 |
||
| 12日(金) |  |
じゃこなめし こうやどうふのあげに みそしる ひとくちみかんゼリー 牛乳 |
|
今日の給食は、雑魚菜飯、高野豆腐の揚げ煮、味噌汁でした。「じゃこ」は漢字で「雑魚」と書くので魚ということはわかるかもしれませんが、使われている魚は何なのか。今回はじゃこについてのお話しです。実は、「ちりめんじゃこ」の雑魚は皆さんもよくはご存知の「しらす」を乾燥させたものなんです。しらすは水分量(乾燥の度合い)によって全て名称が異なり、一般的に釜揚げ(煮沸)した後、水分量を8割以上残したものを「釜揚げしらす」、6割以上残したものを「しらす干し」、5割以下にしたものを「ちりめんじゃこ」と呼ぶそうです。諸説ありますが、ちりめんじゃこの「ちりめん」は、しらすを広げて干した際に織物の「縮緬(ちりめん)」に似ていたことが由来とされています。普段食べている食材に日本の伝統工芸の名称が使われているだなんて、なんだか誇らしいですね!今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 16日(火) |  |
ごはん あじのこうみソースかけ ごもくきんぴら みそしる オレンジ 牛乳 |
| 今日の給食は、ご飯、鯵の香味ソースがけ、五目きんぴら、みそ汁でした。以前、ご紹介しましたが、「きんぴら」の語源は、人形浄瑠璃の主人公、坂田金時(さかたのきんぴら)です。金太郎で有名な坂田金時の息子と設定された、怪力で勇敢な主人公で「強いもの」のたとえと言われています。坂田金平の勇ましさと、ごぼうのしっかりした歯ごたえや唐辛子の辛さが結びつき、「きんぴら」という言葉が強いものの代名詞となっていきました。ごぼうは江戸時代から精がつく食材と考えられていたため、坂田金平のように強くなれるという願いが込められて「きんぴらごぼう」と呼ばれるようになったとも言われています。今日の給食も歯ごたえがあって、おいしかったです。 | ||
| 17日(水) |  |
ハヤシライス ワンタンチップスサラダ パインアップル 牛乳 |
|
今日の給食は、ハヤシライス、ワンタンチップサラダでした。学校給食の人気メニューランキングでは、カレーライスが圧倒的1位で、ほとんどの学校で提供されます。しかし、ハヤシライスは給食に出る機会が少なく、人気もカレーほどではありません。その理由は、どんな点にあるのでしょうか。考えられることは、酸味の強さが子どもに不評だということのようです。ハヤシライスにはトマトケチャップやデミグラスソースが使われるため、酸味が強く感じられることがあります。子どもは甘みのあるカレーのほうを好む傾向があり、酸味のあるハヤシライスは苦手と感じる場合もあるようです。大人とは違う感性がありますね。 |
||
| 18日(木) |  |
ごまみそつけめん ししゃものからあげ だいこんときゅうりのピリッとあえ ミニチーズドック 牛乳 |
|
今日の給食は、ゴマ味噌つけ麺、ししゃものから揚げ、大根ときゅうりのピリッと和え、ミニチーズドックでした。一般的に、ラーメンの大盛りは有料ですが、つけ麺の大盛りは無料というお店が多いことがあります。なぜでしょうか。調べてみると、ラーメンと比べてつけ麺は大盛にしてもラーメンほど原材料費が上がらないそうです。ラーメンはスープにお金がかかっているようです。また、大盛を無料にすることでより多くのお客さんに来てもらえることを考えれば、そこのコストアップは吸収しようというのがつけ麺の基本的な戦略だそうです。事実、大盛無料のお店では多くのお客さんが大盛を注文しています。さまざまなものの値段が上がる昨今、従来のつけ麺の戦略を今後も続けてほしいものです。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 19日(金) |  |
メキシカンピラフ クラムチャウダー ひたしあおまめ はちみつレモンゼリー 牛乳 |
|
今日の給食は、メキシカンピラフ、クラムチャウダー、浸し青豆でした。クラムチャウダーの語源は、「二枚貝」を意味する英語の「クラム(Clam)」と「具だくさんのスープ」を意味する「チャウダー(Chowder)」を合わせた言葉です。チャウダーの語源は、フランス語で「大鍋」を意味する「chaudière(ショーディエール)」であるという説があります。大鍋を使って、漁師たちが海で獲れた魚介類や野菜を煮込んで作ったのが始まりとされています。16世紀頃、フランスからイギリスやアメリカに移住した人々によってチャウダーが広まりました。アメリカでは特にニューイングランド地方で発展していき、クリームベースの「ニューイングランド・クラムチャウダー」が生まれました。今日の東部小のクラムチャウダーも具だくさんでとてもおいしかったです。 |
||
| 22日(月) |  |
カリカリきなこトースト ポークビーンズ かいそうサラダ オレンジ 牛乳 |
|
今日の給食は、カリカリきな粉トースト、ポークビーンズ、海藻サラダでした。きな粉の語源は「黄色い粉」で大豆の黄色から名付けられたと言われています。平安時代の辞典『和名抄』にも「末女豆岐(まめつき)」として記載があり、関西ではよく炒った「京風きな粉(こがしきな粉)」、関東では煎りの浅い「関東風きな粉」が好まれる傾向があることなどが挙げられます。きな粉は大豆を炒って粉末にしたものなので、タンパク質が豊富。きなこ100gにはなんと36.7gものタンパク質が含まれています。タンパク質は筋肉だけでなく、健康な皮膚や内臓など身体の組織を作る重要な栄養素です。健康的で美しい身体を作るために、タンパク質は欠かせない栄養素です。積極的に食べたいですね。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 24日(水) |  |
こぎつねうどん やきおにぎり わかさぎのフリッター うめかあえ 牛乳 |
|
今日の給食は、子ぎつねうどん、焼きおにぎり、公魚のフリッター、梅香和えでした。おにぎりは文字通り「にぎった飯」。 武士の携帯食だったにぎり飯が、「お」のつく女性名詞化して「おにぎり」になりました。 おむすびは宮中の女官が使っていた女房詞(にょぼうことば)で、ご飯を固く結ぶことからついたと想像できます。 万物のうみの神「産霊の神(むすびのかみ)」への供え物だったことに由来するという説もあります。また、5月にも紹介しましたが、焼きおにぎりの由来は、戦国武将・上杉謙信が、戦の際に、冷めて固くなったおにぎりを剣の先に刺して焼いて食べたのが始まりであると言われています。今日のおにぎりも、もちろん給食もおいしかったです。 |
||
| 25日(木) |  |
マーボーなすうどん はるさめスープ なし 牛乳 |
| 今日の給食は、マーボー茄子うどん、春雨スープでした。天候の春雨を季語に詠んだ句は多く、『春雨や蓬(よもぎ)をのばす艸(くさ)の道』(芭蕉)や『春雨やゆるい下駄借す奈良の宿』(蕪村)、『宇治川やほつりゝと春の雨』(子規)などが知られています。天候の春雨と、食べものの春雨、双方を想起させる句としては鈴木花蓑(はなみの)の『もつれつゝとけつゝ春の雨の糸』があります。春雨という言葉は艶(つや)やかさ、情の細やかさ、静けさ、しっとりとした趣をもっており、白く細く、はかなげな感のある麺状の食べものをそう名付けたことに、いかにも日本人ならではの情緒、風情が感じられます。さて、食べものの春雨は、中国で生まれたあと、日本には鎌倉時代に伝わり、現代では、国産メーカーがジャガイモやサツマイモのデンプンを用いた春雨を開発したことで広く普及しました。歴史ある食べ物なんですね。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 26日(金) |  |
ごはん さばのピリッとソース ごまあえ まめまめじる オレンジ 牛乳 |
|
今日の給食は、ご飯、鯖のピリッとソース、ゴマ和え、豆豆汁でした。鯖の由来は、大きな口を持つものの歯は小さく、「小歯(さば)」が由来という説があります。また、多くの群れで行動することから、「多く集まった状態」を意味する古語の「さば」に由来するという説もあります。さらに「サバを読む」といった言葉もありますね。鯖は消化酵素を多く含み、他の魚よりも傷みやすいため、魚市場で鮮度が落ちないよう急いで数を数えていた際に数え間違いが多かったことから、「いい加減に数を数えること」や「数え間違い」を「サバを読む」と言うようになったという説があります。最近では、鮮度を保った輸送方法も多くなり、さらにAIなど最新技術を考えると、サバを読めなくなっているのかもしれませんね。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 29日(月) |  |
ロールパン とりにくのレモンソース こふきいも ハムともやしのスープ きっかみかん 牛乳 |
|
今日の給食は、ロールパン、鶏肉のレモンソース、粉ふきいも、ハムともやしのスープでした。「こふきいも」という料理名自体に、特定の歴史的記録は多くありません。しかし、ジャガイモが日本で一般的に食べられるようになったのは、大正時代にあたります。この「こふきいも」ですが、茹でたジャガイモの水分を飛ばすことで、表面のでんぷんが粉を吹いたように見える様子が名前の由来だそうです。特別な調味料がなくても、ジャガイモ本来の甘みやホクホクした食感を楽しむことができます。おそらく、家庭で手軽に作れる料理として、多くの人に、広く親しまれるようになったのですね。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 30日(火) |  |
ひじきごはん あじのてんぷら あおなのちゅうかあえ とんじる 牛乳 |
| 今日の給食は、ひじきご飯、鯵の天ぷら、青菜の中華和え、豚汁でした。ひじきは縄文時代から食されており、平安時代には朝廷への献上品にもなる貴重な海藻でした。ひじきご飯としては、江戸時代から家庭料理として広まり、庶民も食するようになったとされています。現代でも健康的な食事として人気があり、炊き込みご飯、混ぜご飯、惣菜など多様な形で楽しまれています。一般的に健康食・長寿食とされていることから、1984年に三重県ひじき協同組合が旧敬老の日にちなんで9月15日を「ひじきの日」として、制定しています。日本で流通しているヒジキの多くは中国や韓国産の養殖品ですが、日本産のヒジキの多くは天然品だそうです。今日の給食もおいしかったです。 | ||