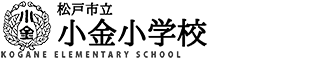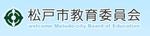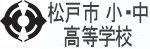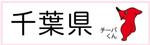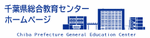災害を意識して
9月の学校だよりでも少しふれましたが、ここのところは「防災意識」を高めていかなければならない状況が続いています。令和6年は元旦の能登半島地震から続く各地での地震の頻発。8月には宮崎県、関東地方でも神奈川県で強い地震があり、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発表も出されました。防災意識を高めるために9月1日は「防災の日」となっていますが、今年は関東大震災が起きてから101年。災害への意識を学校でもより高めるために9月1日は日曜日で避難訓練が実施できなかったので、本日、避難訓練を行いました。
学期始まりでしたので、今回は2時間目の終わり間際で皆が一緒にいる状況で行いました。


授業時間とはいっても、教室にいる場合もあれば、音楽室などの特別教室、体育館の場合もあります。その場所に合わせた第一次避難がとても大切です。教室では、机の下にもぐるだけでなく机の脚をしっかりおさえる姿もありました。音楽室では、椅子に頭を入れて守る子、音楽バックで頭を守る子の姿がありました。机がない場所、防災頭巾が手元にないときにはどうすべきか、頭を守るという意識をもつことは大事なことです。体育館では2年生が学年活動をしていましたが、「ものが落ちてこない」「倒れてこない」場所を意識して体を低くし頭を守る姿がありました。


一次避難・点呼等を行った後に、子供たちに私から「防災の日」を含めた以下の話をしました。


101年前の9月1日に関東地方(南部)で大きな地震「関東大震災」があったこと、時間はちょうど昼頃(11時58分)で大きな建物が倒れたり、あちこちで火事がおきたこと、海では津波がやってきたり、山では大きな土砂崩れもおきたこと、その地震の恐ろしさは立っていられないほどのすごい揺れであったこと。そのときにはたくさんの人が亡くなりとても大きな被害を受けたので、一人一人に災害が起きたときや備えをどうすればよいかの大切さをみんなにしってもらうために、9月1日が「防災の日」となったということ。地球は生きていて、地震はこれでなくなるということはない、だからこそ、小金小の皆にはしっかりと備えをしてほしいということ。
今年の1月1日の元旦には、能登半島でも大きな地震が起きました。夕方の4時10分に最大震度7というとても大きな地震で、家もくずれ、火事もあり、命をなくした人もいます。そして、夏休み中の8月には、私たち千葉県のすぐそばの神奈川県でも大きな地震がありました。夜の7時57分でした。
令和6年になってから大きな地震が続いていて、いつ地震が来るかわかりません。学校で皆と一緒にいるときやお家で家族と一緒にいるときならばよいですが、学校に来るとき、帰るときの途中とか家に帰って外で遊んでいるときにくるかもしれません。だから、小金小の皆さんには次のことに注意してほしいという話もしました。
・学校や家にいるときは、丈夫な机の下などに避難して頭を守ること。
・机がなければ、今日音楽室や体育館でのように「頭を守る」ということが大切。
・固定されていないものが動いてくることもあるので、ものが「移動してこない」ところに避難すること。


ポイントは、「物が落ちてこないか」「倒れてこないか」「移動してこないか」です。「物が落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」場所で自分の身を守るように話しました。外にいるときはブロック塀などが倒れてこないか、海や川のそばにいるときは、急いで高い所へ避難することも併せて話しました。
また、家族で話し合って避難する場所を確かめておくことをお家に帰ってするように話しましたので、ご家庭でも是非、話題にし、非常時の対応等について再度確認をしていただきたいと思います。
画像のように、どの教室、特別教室でも、子供たちは私の話をしっかりと聞いていました。「自分の身は自分で守る」意識をもち、高めていきたいと思っています。