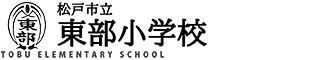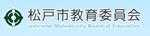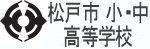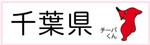10月の給食
| 1日(水) |  |
カレーライス にんじんドレッシングサラダ オレンジ 牛乳 |
| 今日の給食は、カレーライス、人参ドレッシングサラダでした。人参ドレッシングの人参には、β-カロテンの抗酸化作用による免疫力向上や美肌効果、また、油と酢を組み合わせることで栄養素の吸収率が高まる効果が期待できます。特に、体内でビタミンAに変換されるβ-カロテンは、皮膚や粘膜を健康に保つだけでなく、動脈硬化予防やアンチエイジングにも役立ちます。さらに、ビタミンB群や食物繊維なども含み、高血圧や高血糖、コレステロールのコントロールにも効果が期待できる健康食品です。積極的に食べたいですね。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 2日(木) |  |
かきたまうどん きびなごポテトフライ だいこんときゅうりのナムル あましょく 牛乳 |
|
かき玉うどんは具材が細長くカットされていて、うどんと一緒におはしでつかみやすいように工夫をされていました。具だくさんで身体があたたまりました。きびなごポテトフライはしっとり衣なのですがまわりはカリッとしていてとても美味しかったです。甘食は外はカリッと中はふわふわで、ほのかな甘みが牛乳とベストマッチでした。今日もごちそうさまでした。 |
||
| 3日(金) |  |
ちゃめし おでん ごまあえ きなこまめ 牛乳 |
|
今日は、10月に入り少し涼しくなることを予想したメニュー「おでん」です。だいこんにこんぶ、さつまあげにちくわぶ。つみれに厚揚げ、にんじんに、こんにゃく等、たくさんの種類が入ったおでんでした。そして、おでんといえばちゃめし。おでんのつゆとちゃめしが絶妙にマッチしておいしさがふくらみます。今日は、秋を食で感じるメニューでした。 |
||
| 6日(月) |  |
さんまごはん のっぺいじる かんぴょうのごまずあえ じゅうごやデザート 牛乳 |
|
今日の給食はさんまご飯、のっぺい汁、干ぴょうのごま酢和えでした。 さんまの2025年は、シーズンの早い時期から例年をはるかに上回る水揚げが記録されました。北海道や岩手などの主要な漁港では、昨年比で2倍以上の水揚げが報告されています。ただ漁獲量が多いだけでなく、大ぶりで脂ののりが良い、質の高いサンマが多いことも今年の話題になっています。豊漁により、サンマの価格は例年よりも大幅に安くなりました。昨年は1匹500~600円だったものが、今年は300~400円程度で販売されるなど、消費者にとって手が届きやすい価格になっています。給食にもやっと出せる金額になってきたというところですね。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 7日(火) |  |
みそカツどん すましじる からしあえ きっかみかん 牛乳 |
|
今日の給食は、みそカツ丼、すまし汁、からし和えでした。みそかつの起源には諸説ありますが、有力な説は、戦後間もない名古屋の屋台で生まれたという説が有力です。老舗がいくつか存在しますが、「矢場とん」の創業者は、戦後の屋台で客が串カツをどて煮のタレにつけて食べているのを見て、これをメニューに取り入れたことが始まりだと言われています。どて煮は、牛すじや豚のモツなどを豆味噌とみりん、砂糖などで甘辛く煮込んだ名古屋の郷土料理です。現在では、みそかつのタレは各店舗で独自の配合がされており、カツ丼としてだけでなく、定食や串カツ、ハンバーガーなど、様々な形で楽しむことができます。今日の東部のみそかつも独自の調合です。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 8日(水) |  |
ホイコーローどん もずくとたまごスープ ポテトとだいずのあまずあえ 牛乳 |
|
今日の給食は、ホイコーロー丼、もずくとたまごスープ、ポテトと大豆の甘酢和えでした。5月と7月に出ているリピートメニューのホイコーローですね。ホイコーロー発祥地である中国四川省の料理に欠かせない調味料といえば、もちろん豆板醤。甜麺醤(甘味噌)も使用されることが多く、甜麺醤は甘辛い独特の風味が特徴です。同じホイコーローでも広東省では、四川のものに比べて甘さが強調されています。豆板醤は控えめで、甜麺醤や砂糖を多く加えて、まろやかでコクのある甘辛いソースに仕上げます。豚肉の部位も異なり、より脂身の少ない豚肩ロースが使われ、軽い食感を重視するため、強火でサッと炒めることが特徴だとか。同じ料理でも味付けが違うのが、面白いですね。機会があれば、次は上海のホイコーローについて書きたいと思います。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 9日(木) |  |
ごはん にくどうふ ししゃものいそべあげ あおなのちゅうかあえ りんご 牛乳 |
|
今日の給食は、ご飯、肉豆腐、ししゃもの磯部揚げ、青菜の中華和えでした。肉豆腐は京都発祥の煮込み料理で、精進料理の背景と、京都の牛肉文化が融合した料理です。奈良時代に中国から日本へ伝わったとされる豆腐は、かつて貴重なタンパク源として僧侶の精進料理に取り入れられ、特に京都で豆腐作りが発展しました。その一方で、関西、特に京都の牛肉文化と結びつき、牛すき焼き発祥の地とも言われる京都で、肉と豆腐を合わせた肉豆腐が家庭や料亭で広く作られるようになりました。今では、それが広がって家庭料理になったのですね。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 10日(金) |  |
コッペパン ブルーベリージャム さつまいもとしめじのシチュー かいそうサラダ だいずこざかな 牛乳 |
|
今日の給食は、コッペパン、ブルーベリージャム、さつま芋としめじのシチュー、海藻サラダ、大豆小魚でした。ブルーベリーの歴史は北アメリカで始まり、先住民が野生種を食用や薬として利用したことにさかのぼります。商用栽培が本格化したのは20世紀初頭で、特に1916年の初の商業収穫が歴史の転換点となりました。第一次世界大戦中の英国のパイロットがブルーベリージャムで夜間視力が向上したと証言したことがきっかけで、日本に導入・普及されたのは20世紀後半で、現在は世界中で栽培される果物です。ブルーベリーに含まれる色素である「アントシアニン」が脳血管障害を予防したり、視機能を改善したりするということが分かっています。また、目や皮膚、鼻や喉などの粘膜を保護してくれるビタミンAも、豊富に含まれています。それもブルーベリー=目に良い、と言われる情報に拍車をかけたのかもしれません。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 14日(火) |  |
ごはん さけのたつたあげ くきわかめのきんぴら まめまめじる きっかみかん 牛乳 |
|
今日の給食は、ご飯、鮭の竜田揚げ、茎わかめのきんぴら、豆豆汁でした。鮭の竜田揚げは、7月に一度出たリピートメニューですね。竜田揚げの名前の由来は、諸説ありますが、百人一首にも収録されている和歌「千早ぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは」に由来しているそうです。この歌は、平安時代の歌人・在原業平(ありわらのなりひら)で、「神代の昔にも聞いたことがないほど、竜田川の紅葉が、川の水を真っ赤な絞り染めのように染めているとは…」という驚きと紅葉の美しさを表現した歌です。からりと揚がった衣に透けて見える醤油色(=紅い色)とその上に浮かぶ白い点模様を『竜田の錦』=『紅葉』に見立てて命名された風情ある日本料理の名前なのですね。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 15日(水) |  |
サフランライス・ポークストロガノフ コーンサラダ パインアップル 牛乳 |
|
今日の給食は、サフランライス、ポークストロガノフ、コーンサラダでした。ポークストロガノフの起源は、ロシア発祥の「ビーフストロガノフ」にあります。ビーフストロガノフはロシアの貴族ストロガノフ家が考案したとされ、ポークストロガノフはこのビーフストロガノフを豚肉で作った派生料理です。ストロガノフ伯爵家が主催する「開かれた食卓」で、フレンチの料理人が考案したという説が最も有名です。また、歯を失って好物のビーフステーキを食べられなくなったストロガノフ伯爵のために、薄切りにした牛肉をサワークリームソースで煮込んだという説もあります。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 16日(木) |  |
きなこあげパン マカロニスープ とりにくとひよこまめトマトに オレンジ 牛乳 |
|
きな粉揚げパン、マカロニスープ、鶏肉とひよこ豆のトマト煮でした。鶏肉とひよこ豆のトマト煮で出た、ひよこ豆。ひよこ豆は、トルコ南東部を起源とするマメ科の植物で、ひよこのくちばしに似た突起がある形が特徴です。タンパク質、食物繊維、葉酸、ビタミンなどが豊富で、栗のようなホクホクした食感と素朴な味わいが特徴です。カレー、スープ、サラダ、フムスなど、幅広い料理に活用され、近年日本でも人気の食材となっています。今日の鶏肉とひよこ豆は、トマトとの相性が抜群でした。ちなみに、きな粉揚げパンは、どのクラスでも残りのパンを争奪戦になっていました。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 17日(金) |  |
あきのかおりごはん たちうおのたつたあげ ごまあえ みそしる ひとくちぶどうゼリー 牛乳 |
|
秋の香りご飯、太刀魚の竜田揚げ、胡麻和え、味噌汁でした。太刀魚は細長い銀色で、その姿から「太刀魚」と呼ばれ、立ち泳ぎをする姿も特徴です。体表は鱗がなく、キラキラした銀粉(グアニン)で覆われています。旬は夏から秋で、刺身や塩焼きで美味しく、DHAやEPAといった栄養素も豊富です。また、体表の銀色はラメや人工真珠の原料にも使われています。鎌倉幕府を倒した武将の新田義貞は、鎌倉攻めにあたり、引き潮を祈願して稲村ケ崎の海に太刀を投じ、勝利への突破口を開いたいう話があります。太刀魚はその太刀の生まれ変わりとする故事があり、川柳にもよまれています。歴史と関係の深い魚なんですね。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 20日(月) |  |
カレーうどん やきしおむずび ポップビーンズ きりぼしだいこんうめサラダ 牛乳 |
|
今日の給食は、カレーうどん、焼き塩むずび、ポップビーンズ、切干大根梅サラダでした。水に戻すだけでお手軽に調理ができて、常備菜として重宝する切干大根。煮物からサラダまでアレンジ自在な万能食材です。子どもからお年寄りまで幅広く愛されていますね。秋から冬にかけて収穫した大根を千切りにして、天日で干したものを切干大根といいます。切り方によって名称が異なり、定番の切干大根のほかに大根を縦割りにした「縦割大根」や短冊切りにした「平切り大根」、輪切りにした「花切大根」などがあります。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 21日(火) |  |
ごはん たまごふりかけ ちくぜんに みそしる みかん 牛乳 |
|
今日の給食は、ご飯、卵ふりかけ、筑前煮、みそ汁でした。筑前煮の起源は、現在の福岡県にあたる筑前国にあります。元々は「がめ煮」という名前で親しまれていた郷土料理でした。その名前の由来には諸説ありますが、博多弁で「寄せ集める」を意味する「がめくり込む」から来ているという説があります。また、文禄の役(1592年)の際に、豊臣秀吉の朝鮮出兵に参加した兵士たちが、スッポン(当時は「どぶがめ」と呼ばれた)と手に入る野菜を煮込んで食べたのが始まり、という説も有力です。いずれにせよ、時代とともに手に入りやすい鶏肉が主流となりました。この「がめ煮」が、学校給食を通じて全国に広まる過程で、「筑前煮」という名称が定着したと考えられています。福岡では今でも「がめ煮」と呼ぶのが一般的で、正月料理や祝い事には欠かせない、まさに“ソウルフード”なのだそうです。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 22日(水) |  |
ごはん さばのみそに なめたけあえ かきたまじる かき 牛乳 |
|
今日の給食は、ご飯、サバの味噌煮、なめたけ和え、かきたま汁でした。秋が旬の魚と言えば、さんまや鮭が有名ですが、鯖も忘れてはならないおいしい魚のひとつです。この時期に獲れた鯖は「秋鯖」と呼ばれ、脂ののりが良く、味も格別と高い人気があります。秋から冬にかけて鯖がおいしくなる時でもあります。余談ですが、定食屋さんなどで鯖の煮付を注文すると、東京では赤味噌で仕上げられた煮付が登場します。しかし、大阪では醤油ベースの出汁で仕上げられた品が提供されています。関西でも、味噌煮はありますが、その場合は鯖の味噌煮と表記されるお店が多く、鯖の煮付という文言は、醤油煮を指すそうです。話は逸れましたが、今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 23日(木) |  |
アップルトースト ポトフ ひたしあおあめ 牛乳 |
|
今日の給食は、アップルトースト、ポトフ、おひたし青豆でした。ポトフは、フランスの伝統的な家庭料理で、地域や家庭によって具材や作り方が異なるのが特徴です。名前の由来は「火にかけた鍋」(pot-au-feu)。フランス語の「pot(鍋)」と「feu(火)」を組み合わせたものとなります。本場では肉と香味野菜を塩で煮込みますが、日本ではソーセージや他の肉、多様な野菜が使われることがあります。また、ポトフは具材とスープを別々に盛り付け、マスタードなどで味付けして食べるのが本場流で、残ったスープを翌朝の雑炊にしても美味しいとされています。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 24日(金) |  |
シーフードピラフ ミネストローネスープ だいがくいも 牛乳 |
|
今日の給食は、シーフードピラフ、ミネストローネスープ、大学芋でした。大正初期、東大の赤門前に三河屋という、ふかし芋の店があったそうです。あるとき、この店でサツマイモを揚げてミツをつけて売ったところ、学生に大好評で飛ぶような売れゆきで、以来、ミツ付きの揚げ芋は三河屋の定番メニューになり、大学前で売っている芋ということで誰いうとなく「大学芋」という言葉が生まれたそうです。また別の説によれば、東大生販売説(昭和初期)。東大の学生が学費を捻出するため、大学の門前で中国の「抜糸紅薯(バースホンシュー)」を参考にした芋を売ったことから「大学芋」と呼ばれるようになったという説もあります。さらに、早大起源説というものもあるのだとか。はたしてどれが大学芋の起源なのでしょうか・・・。調べてみると、面白いですね。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 28日(火) |  |
ごはん いなだのてりやき はるさめサラダ みそしる きっかみかん 牛乳 |
|
今日の給食はご飯、イナダの照り焼き、春雨サラダ、みそ汁でした。イナダは出世魚で、ブリになりますね。関東では、稚魚の順から「モジャコ」→「ワカシ」→「イナダ」→「ハマチ」→「ブリ」と呼ばれます。関西では「ツバス」→「ハマチ」→「メジロ」→「ブリ」、九州では「ワカナゴ」→「ヤズ」→「ハマチ」→「メジロ」→「ブリ」→「オオブリ」など挙げきれないほどの名前があります。それだけ、日本人になじみが深く、広く愛された魚ということなのですね。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 29日(水) |  |
まるパン はなまめコロッケ ボイルキャベツ コーンクリームスープ ひとくちりんごゼリー 牛乳 |
|
今日の給食は、丸パン、花豆コロッケ、ボイルキャベツ、コーンクリームスープでした。コロッケの名前の由来は、フランス語の「クロケット(croquette)」からきています。「バリバリ食べる」という意味の「croquer(カリッとした音を出してかじる)」「クロケ」が変化したものだと考えられています。クロケットは、17世紀のフランスで宮廷料理として登場しました。また、これが明治時代に日本へ伝わり、庶民の味であるジャガイモを使った日本の家庭料理として変化しました。今では大正時代の「大正三大洋食」の一つとして親しまれています。今日の給食もおいしかったです。 |
||
| 30日(木) |  |
わかめごはん なまあげのごまだれかけ こぶちゃあえ とんじる 牛乳 |
| 今日の給食は、わかめご飯、生揚げのゴマだれかけ、昆布茶和え、豚汁でした。生揚げは、木綿豆腐を高温の油で揚げることで表面が香ばしいきつね色に仕上がった豆腐製品で、中は豆腐の柔らかさを残しています。油揚げとの違いは、内部までしっかり揚げずに豆腐の状態を保つ点にあります。東日本で「生揚げ」、西日本では「厚揚げ」と呼ばれることが多く、煮物、炒め物、おでんなど幅広く使われる便利な食材です。その起源は江戸時代にまでさかのぼり、豆腐の保存性を高めるために揚げたのが始まりとされています。現在では、海外でも「Fried Tofu」や「Tofu Puffs」として販売されています。東南アジア料理では、カレーやスープの具材として使われており、欧米では、ビーガンやベジタリアン向けのタンパク源として注目されています。今日の給食もおいしかったです。 | ||
| 31日(金) |  |
わふうボンゴレスパゲティ サクサクポテトサラダ チョコっとかぼちゃケーキ 牛乳 |
| 今日の給食は、和風ボンゴレスパゲティ、サクサクポテトサラダ、チョコっとかぼちゃケーキでした。ボンゴレとは、「アサリ等の二枚貝」のことを指します。「ボンゴレ・ビアンコ=アサリ等の二枚貝を使った白いパスタ」を意味します。この場合の「白」とは「トマトを使わないもしくはクリームソース系」を指します。ピッツァでも、お店によっては「ビアンコピッツァ=トマトソースを使わないピッツァ」とメニュー表記しているところもあります。ちなみに、トマトソースをからめたものは「ボンゴレ・ロッソ」と言います。「ロッソ=赤」の意味です。さらに、ジェノヴェーゼをからめた緑色の「ボンゴレ・ヴェルデ」、イカスミ仕立ての「ボンゴレ・ネロ」という料理もあります。今日の給食は「和風ボンゴレ・ビアンコ」とも言えますね。今日の給食もおいしかったです。 | ||