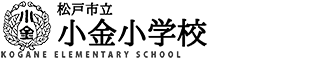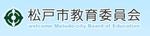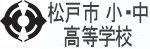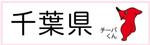キャリア教育で大活躍のパパさぽさんと土曜参観・引渡し訓練への御礼
本日は、土曜参観にたくさんの保護者の皆様にご来校いただき、ありがとうございました。
全校の授業参観は3校時に設定していましたが、6年生は1、2校時にパパさぽさんに支援をいただき、「キャリア教育」の学習をしました。
「キャリア教育」とは、「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通してキャリア発達を促す教育(中教審答申より)」とされています。端的に言えば、「社会的・職業的自立に向けた教育」とでも申しましょうか。将来、社会に出ていくために「自分の役割を果たして活動すること」や「自分らしい生き方」を考える学習で、「総合的な学習」に位置付けています。
そのような、「将来の自分らしい生き方」を子供たちの身近な大人である「パパさぽ」さんから、職業についてや仕事の様子、仕事への思いや楽しさなどを聞かせていただき、将来、何ができるか、そのために今から何ができるかを考える充実した時間でした。






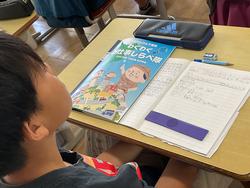
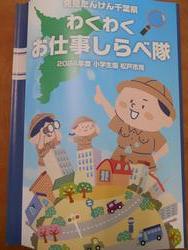
6年生の子供たちは、身を乗り出して話を聞いたり、質問したりし、「働くことへの期待」や「未来」に向けてイメージを膨らませ、考えている様子がうかがえました。また、学んだことを「わくわくお仕事しらべ隊」に記入し、それぞれの気付きや思いをまとめていました。
パパさぽさんたちの、「やりたいことが今決まっていなくても、後から決められるように自分で準備をしておこう。そのために勉強は必要だよ。」という言葉が、学校での学習や家での学習につながっているということも実感できました。仕事をしていて嬉しいのは「目標を設定して達成したとき」であり、「相手のことを考えて仕事をしている」、「コミュニケーションの大切さ」というお父さんの言葉がとても印象的でした。目指すところは、学校教育と同じ。パパさぽさんからのお話が学校教育とつながっていることを再認識した喜びもありました。本当に、パパさぽさんたちの「キャリア教育」へのご協力に感謝いたします。
3校時は、全学年の授業参観でした。今年度は、学年始まりにもきっと新しい担任が行う授業を参観されたいであろうと思い、新たに4月に授業参観を設定しましたので、今回は1時間の授業参観設定とさせていただきました。たくさんのご参観をありがとうございました。
グループ発表、一人一人が自分の考えをしっかりと書いたり説明したりする活動、中には土曜参観ならではの英語で質問をお家の方に質問したり計算練習をお子さんのそばに来てもらってお家の方と一緒に問題を考えたりする活動などの授業展開を行いました。子供たちもお家の方々がいらっしゃるので張り切って授業に参加していました。





また、今日は保護者の皆様に、その後の午後にも避難訓練後の引取り訓練にもご協力をいただきました。
子供たちの避難の仕方については、今回は「おしゃべりをしないこと」は課題として話をしましたが、保護者の皆様の引取り訓練へのご協力の姿には頭が下がりました。
私は、「訓練のための訓練」であってはならないと考えています。今回の最大の目的は、「災害時を想定した児童のスムーズな引取り」です。

そのため、地震が本当に起きたときを想定して「避難後の保護者引取りが必要」と判断してからのメール送信となっています。実際の災害では、メールや電子機器による連絡が難しいのは、東日本大震災でも経験があります。また、混乱による二次的混乱はさらなる災害を生みます。今回、引取りに来てくくださった皆様へお話してお願いしたのが以下の3点でした。
①引取り者であるかどうかの確認をきちんと行うこと(災害時では担任が把握してないご家族の方等が引取りに来ていただくこともあり得ます)
②順番や引取り後のルートの確認をし守ること(混雑をしているときにきちんと守ることが混乱を防ぎます)
③学校外でも災害を想定し、通学路の点検及び学校外での災害時の動きをご家庭内での確認(災害は学校教育課程外の方が多いです)
保護者の皆様が、引取り訓練の趣旨をご理解の上、整然と私語もなくスムーズに引取りが行えたことに大変感謝いたします。
能登半島の地震で始まった令和6年。ここのところは、千葉県東方沖での地震も度々あります。どうぞ、改めてご家庭でも話し合っていただきご確認ください。
今日は1日、朝から、パパさぽさんによるキャリア教育から始まり、授業参観、引取り訓練と小金小の行事にご理解・ご協力いただき、本当にありがとうございました。10日(月)は振替休業、11日(火)には、元気な子供たちにまた会えるのを楽しみにしています。